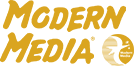バックナンバー
Back Number
2018年6月号(第64巻6号)
〇弱々しい光を帯びたうす水色の空が広がる梅雨。高層ビルの屋上から立ち昇る冷却塔からの白煙は輪郭も曖昧で、ゆっくりと空に吸い込まれ、そのまま雲になってしまいそうである。
〇傘の英語“umbrella”の語源は「影」という意味の“umbra”である。語源からもわかるように、西洋では古く「傘」といえば日傘であった。18世紀後半、旅行家でもあり商人でもあった英国出身のジョナス・ハンウェイは、他国で洋傘を雨傘として使っているのを知り、ロンドンの町を独り、雨傘を差して歩いた。だが、日傘が女性特有の持ち物であったために「男がペチコートを履いているようだ」と嘲笑され、世人に受け入れられるまでには時間がかかったようである。のちに傘の柄を、男性にとって馴染みのあるステッキ形にしたところ、爆発的に普及したそうである。
わが国では頭上に装着する笠や和傘があり、のちに帽子や洋傘がこれに取って代わり主流となった。「日本書記」(720年完成)にはすでに笠のことが書かれており、約200年後に完成した当時の辞書「和名類聚抄」には「加佐」という文字が当てられているそうである。
本来傘は、権力の象徴として権力者の頭上にさし掛けられるものでもあり、「かさ(笠)に着る」の用語は権力者の力に頼って威張ることである。意味が混同されがちな「かさ(嵩)にかかる」はかさばる意味のほうで、優勢の者が勢いに乗じて威圧的になることである。
〇江戸時代の浮世絵師 歌川広重(寛政9年(1797)-安政5年(1858))は、「東海道五拾三次」の木版画を残したことでも有名である。起点の江戸日本橋から終点の京都三条大橋を結ぶ東海道は、53次(53箇所の宿場)を包括していた。
このうち「庄野 白雨」の作品では、品川宿から数えて45番目の宿場にあたる庄野の宿近く(現在の三重県鈴鹿市のあたり)の街道で、夏のある日、突然の雨に見舞われた籠屋や農民、町民と思しき数名が目的地へと急ぐ様子がいきいきと描かれている。何の変哲もない街道の風景が、突然の雨によって一転、ドラマチックな舞台へと変貌を遂げた瞬間である。
竹藪だろうか、街道沿いの木々という木々がなだれかかるような激しい風雨のなか、籠屋の二人は揃いの黒い籠屋笠、お客には、籠全体を覆うほどの大きな布をかけ、激しい雨に負けるものかと坂道を駆け登る。籠屋の前には、唐傘お化けと見紛うような足の生えたムシロが走る。半円球形の笠を被った男は、蓑をまとったキノコのようないでたちで、転げおちるように坂道を駆け下りていく。
険しい坂道を登る者下る者、突然の雨の中でみんな急ぎ足である。ただ唯一、所々破れた番傘で雨に立ち向かう者だけが、ややゆとりをもって歩いているように見て取れる。
いつ天気が崩れるか分からない梅雨の日々、面倒でも常に雨傘を携帯するのが一番、転ばぬ先の杖である。