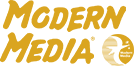バックナンバー
Back Number
2014年6月号(第60巻6号)
〇蒸し暑い季節になった。これだけ雨も多く湿度の高い6月の異名が「水無月(みなづき)」であるのは意外だが、「無」には語と語の関係を示す格助詞の「の」の役割があり、田植え後、田に水を張る時期であることから「水の月」を意味しており、他にも「水月」「水張月」などの呼び名もあるという。また、田植えの仕事をすっかりし尽くした「皆仕尽(みなしつき)」を由来とする説などもあり、何が正しいのかは定かでない。
〇6月と12月の晦日には、日本各地の神社で「大祓(おおはらえ)」という行事が行われる。古代の法典「大宝律令(701年)」で定められた宮中の儀式でもあり、日頃意識せずに犯してしまう“罪穢災厄”を取り除く神事である。半年に一度行われることから、「二季の祓」ともいわれ、6月の行事は「夏越の祓(なごしのはらえ)」、12月の行事は「年越しの祓(としこしのはらえ)」と呼ばれ、区別されている。
「夏越の祓」では、茅の葉を束ねて作られた、人が一人潜(くぐ)れるほどの輪が神前に立てられ、「はらいたまい、きよめたまえ」と祈りを捧げつつこの輪をくぐれば穢れが清められ、疫病にも負けない力が宿るとする「茅(ち)の輪くぐり」という習わしが行われる。
ことの起こりは、武塔神(むとうしん)(須佐之男命(すさのおのみこと))が嫁取りのため南海を旅する途中、蘇民将来という神に一夜の宿を借り、貧しいながらも心を尽くしたもてなしを受けた御礼にと、疫災を取り払う茅の輪を蘇民将来に授けたとする説話に由来するといわれる。茅の生命力の強さが無病息災に結びついたもので、疫病が流行すると人々は茅の輪を身につけ、自分が蘇民将来の子孫であると呪文を唱えたという。
「母の分ん も一つ潜る ちのわ哉」 小林一茶
これは、小林一茶(1763-1828)が日々の出来事を句で綴った「八番日記」に文政3(1820)年、一茶が57歳のときに書かれた句である。一茶は、生母とは3歳で死別し、8歳で迎えた継母とは不仲で15歳で故郷の信州から江戸に上京している。父の死後十数年もの間、遺産相続を巡り継母と争ったというが、母を想いもう一度茅の輪を潜った一茶の心には、継母への複雑な想い、あるいは亡き母への想いが溢れていたのか、私は真相を知らない。
〇京都や関西では、茅の輪くぐりにあわせ、三角形の外郎(ういろう)の上に小豆を乗せた「水無月」という和菓子を食す習慣があると聞いた。小豆、三角の形にも厄除けの意味があり「夏越の祓」が行われる6月の晦日に向かう短い期間に限り、この菓子を販売している店が多いようだ。
平安時代から室町時代にかけて、庶民には手に入らなかった氷室の氷が幕府や朝廷に献上される行事を真似て、庶民は知恵を絞り安価な外郎を氷室の氷にたとえ、この菓子を作った。恐らく、何不自由なく暮らす現代人とは比べ物にならないほどの想像力をもって勝ち得た涼を感じていたのである。工夫が凝らされた小さな和菓子から、様々な便利なものと引き換えに、厳しい季節を乗り越える知恵や季節の趣を楽しむ心の豊かさが、気づかぬうちに失われていく危うさに気づかされた。