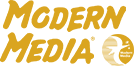バックナンバー
Back Number
2013年8月号(第59巻8号)
〇8月のある晩、行き場を失くしたように街中を漂うむっとする熱気のなかに、花火を燃やす時に立ち昇る火薬の香りを感じた。住宅街の一角、どこかの子供が庭先で花火を楽しんでいるのだろう…。とっさに線香花火のどこかはかなげなちりちりとした火花が思い浮かんだ。
線香花火の形には、竹ひごや藁の先に火薬を付けた「すぼ手」と、和紙に火薬を包みこみ、持ち手をこより状に撚った「長手」の2種類がある。関西は「長手」、関東は「すぼ手」が主流だそうで、関東出身のわたしは「すぼ手」のほうを思い浮かべる。
火花の状態は時間と共に移り変わるが、これにはそれぞれ呼名が付けられており、先端に火の玉ができる状態を「牡丹」、ぱちぱちと火花を散らす盛りを「松葉」、火花が鎮まる頃を「柳」、消える寸前のわずかな華やぎを「散り菊」という。これらの呼名といい、火花を長持ちさせようと息をこらし、花火の先をじっと見守るひとときもまた風流である。
〇安藤広重の「名所江戸百景」には両国の川開きの様子が描かれている。ゆるやかなアーチ型の橋の上にはたくさんの人の姿、橋によって分かたれた川の左右には思い思いの場所に屋形船を停めて打ち上げ花火を見物する乗客の姿がある。橋の向こうに描かれている川岸からかなりの上空、ちょうど画を縦横で4つ切りにした右上あたりの空に片寄せられたように花火が上がっている。まるで夜空に咲き誇る菊の花畑、あるいはコバルト色の空に施された江戸切子の細工ようにも見え、幻想的である。
両国の花火は、もとは凶作や疫病でたくさんの死者が出たことから、慰霊と悪疫払いのため行われた水神祭(1731年)の際、川の両岸の水茶屋が余興として花火を上げたことが始まりとされる。今では夏の行事として欠かせない隅田川花火大会の前進である。
〇花火が日本に伝わったのは、鉄砲伝来(1543)によって火薬の配合が伝わった後のことで、当初は唐人や宣教師など外国人によって花火の行事が執り行われていた。1600年代初頭になると花火師が現れ、やがて子供相手に撚花火・線香花火を売り歩くようになったそうだ。古い書物には「花火花火、鼠手、ぼたん、てん車、からくり、花火花火」の呼声があったことも記録されている。
子供らは花火師の呼声をさぞ心待ちにしていたに違いない。魚売、豆腐売、飲物売、金魚売りなど、江戸の町では様々な呼声が飛び交い、当時の人たちは、日々、その呼び声に季節の移り変わりや何かをするのにちょうど良い頃合に気付かされていたことだろう。
操縦席を時間に奪われ、慌ただしい毎日を送る現代人ではあるが、花火の美しさに見惚れ時間を忘れるひとときは、風雅を解するわが国に生まれたはるか昔の人たちと心をひとつにできる瞬間でもある。