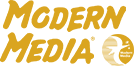バックナンバー
Back Number
2017年6月号(第63巻6号)
酒の味
正月がひっそりと静かだった頃の話である。縁起物だからと小学校に入る前から酒を飲まされた記憶がある。小さな杯に燗酒を注いでもらって飲むのである。祖父は奈良漬で顔が赤くなるほど酒に弱く、父も家では滅多に飲むことは無かったので、皆で酒を飲むなどということは特別だった。おぼろげな記憶ではあるが、その酒は多分うまくなかった。近所にあった造り酒屋は廃業してしまったので、確かめるわけにもいかないが、最近の流行りの酒とは大分味わいが違っていたと思う。
出張先で居酒屋に寄ると、その土地で評判の地酒と土地の肴を注文する。この地酒、最近どこに行っても優等生というようなのが出てくる。爽やかで料理の邪魔もしない。自己主張のないのが自己主張というようなやつである。どうして、どこの土地でも同じような酒になったのか。どこでもいい地酒があるのは喜ばしいが、飴でもあるまいし「どこで切っても金太郎」も考え物である。地酒のもつギャンブル性というか、意外性が楽しみなのだが、毎回優等生が出てくると、ありがたいけど少しがっかりという複雑な気分である。年賀状で切手シートが当たった時に似ている。蔵元としては、販路を海外にまで広げようという時代に、いかに流行りの風味に乗るか、会社の存亡がかかる。うわさに聞けば、評判の良い杜氏集団が味の良い酒を造る麹をもって全国各地を渡り歩き、「良い酒」が全国に普及したというのである。致し方のないことである。
先日、行きつけの店で、すでに出来上がった客がきた。注文は一言「ダラカン」。「ダラカン・・。何です?」と聞くと、「ぬる燗よりも・・さらに・・ぬるいの・だ。」と解説が始まり、成り行きでお相伴した。酔った後の軟着陸まで、だらだら飲むのであった。ここまで来ると味はどうでもよい。
それにつけても、廃業した酒蔵の酒の本当の味を確かめておけばよかった。「多様性の尊重」だの「個性を伸ばす」は、言うは易し、行うは難し、である。