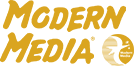バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 病理医の悲哀
2015年6月号(第61巻6号)
病理医の悲哀
本誌5月号に掲載された坂本穆彦先生の随筆の中にある「病理検査/診断」という言葉に思わず反応してしまうのは病理医だけかもしれない。検査ではデータとして現れる結果が伝えられ、これをもとに依頼した医師が判断を下す。病理で言えば、検体を顕微鏡標本にするまでが「病理検査」になるわけだが、作製した標本を「検査結果」として返されても依頼医師は困るだけだろう。病理に求められるのは、標本にみられる所見を元にした「病理診断結果」であり、病理の報告書は「検査結果報告」とは異なるのである。しかし標本作製から病理診断までを含む良い言葉がない。恐らく患者さんに説明するにも「病理の検査結果では」と話す医師が多いことだろう。実はわれわれ病理医は、長らくこの「病理検査」という言葉に苦しめられている。
「病理診断は医行為である」と国が認めているにも関わらず、病理診断業務は「生体検査」の中で扱われてきた。世間に名の知られたある内科医に「病理診断って医者しか出来ないんですか?!」と公然と聞かれて面食らった覚えがある。他科に患者を紹介するのに名前と診断名だけの紹介状を送りつける医者はいないはずだが、患者氏名と「〇〇の疑い」という臨床診断名だけの病理“検査”依頼書が後を絶たないのは、そのような認識によるものだろう。
保健所に届け出る「医師届出表」に病理の項目はなく“その他”の医師扱いの時代が続き、直接患者を診ないという理由で病理は標榜も認められてこなかった。つまり国が病理医の人数や全国での分布を正式に把握する機会はなかったのである。現在、日本の病理専門医の数は2000名余、その平均年齢は55歳、まさしくアホウドリに並ぶ絶滅危惧種になっている。自分たちではDoctor of doctorsなどと粋がっていても、若い研修医から「早くケンサ結果を返してくれないと困るんだけど!」などという電話があるようでは、病理医志望者が増えないのも当然だろう。「病理検査/診断」という言葉に込められた病理医の想いは深い。
この数年の間に、病理診断科が標榜科として認められ、病理専門医は基本診療領域の専門医の1つとなった。診療報酬でも、第3部「検査」第2節「病理学的検査」であったものが第13部「病理診断」として独立し、さらにDoctor’s feeである「病理診断料」の算定も可能となった。遅ればせながら、絶滅に対する保護政策が取られ始めているようだ。多くのひな鳥たちが飛び立つ日を夢見て、病理診断学を確立してきた団塊世代の病理医たちは、定年を超えても働き続けているのである。