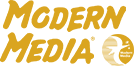バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 細胞診の底力
2015年5月号(第61巻5号)
細胞診の底力
例えば癌検診を受けたところ、細胞診で子宮頸部に扁平上皮癌が検出されたとしても、更に組織診でその判定が裏づけられることが治療開始のためには必要とされる。つまり、細胞診は補助診断、組織診が最終診断という住み分けが病理検査/診断のセントラル・ドクマだからである。日常診療ではこの様に細胞診よりも組織診の方が優位に扱われている。
しかし、これは細胞診の一面にすぎない。診断の根底にかかわる部分では、細胞診は実は大きな力を発揮している。だがこのことは余り知られていない。
細胞診が組織診をリードした例を、子宮頸部でみてみよう。まず、上皮内癌と異形成の用語と定義の確立についてである。“浸潤がなければ癌とはいえない”などの考え方が交錯する中、1960年代に開催された細胞診の国際会議で、上皮内癌を浸潤のない癌、異形成を良・悪性の中間的病態と定義し、実地に運用した。その有用性は組織診でも確認され、後年組織分類にそのまま取り入れられた。また、20世紀終盤にいたり、ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)が異形成や癌の病因として認識された。この流れの中で、1989年に細胞診の側から新しい概念である扁平上皮内病変(SIL)が提唱された。異形成・上皮内癌をHPV感染に関連した病変として一括したものである。この発想は、腫瘍の概念に再検討を求めるほどの画期的なものであったが、それでも徐々に各国に浸透していった。遅ればせながら、我が国でも数年前に細胞診用語として公式に採用された。2014年版WHO組織分類にも遂にSILが組織診断名として掲載された。
この様に細胞診は、病態の本質にかかわる部分ではたえず時代の先を歩んでいる。この事情を知れば知るほど、細胞診が補助診断としての臨床的側面のみで説明されている現状は何とも歯がゆい。ささやかな試みとして、私は著述や講義・講演では“細胞診の意義は単に補助診断にとどまるものではない”、“細胞診と組織診は病理検査/診断の車の両輪である”と述べることにしている。