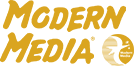バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 記憶の樹林に聳える大樹
2014年9月号(第60巻9号)
記憶の樹林に聳える大樹
この度の原稿依頼に勃然と記憶に蘇ったのは、筑波大学臨床病理学教授、及川淳先生の随筆である。私が講師のころ、先生は五十歳代後半で本来なれば学会の中枢で活躍されるべき逸材でありながら、循環器関連の痼疾に飛躍の機会を阻まれ半ば諦観されていたかとも思われる時期であった。先生がある日、やや遠慮がちに渡された医学雑誌の巻頭言の別冊には「敬存 影岡武士先生」と墨書されていた。冒頭の文章の中に、啄木の歌が引用されていた。「友がみな われよりえらく見ゆる日よ 花を買い来て 妻としたしむ」。及川先生の心情が心に沁みた瞬間であった。
思い出すままに遡及すると、私が臨床病理の領域に足を踏み入れる所縁となったのが、柴田進先生である。日本臨床病理学の開祖とも言うべき渾身の教育者で、頭を白墨の粉で真っ白にしながら黒板に先生の神髄を埋めてゆく姿に感動した。さらに、先生の日常は清貧というに相応しく、未開の原野を行く開拓者の姿であった。柴田先生が山口大学医学部を去られた後、三輪史郎先生が第三内科教授として赴任され血液内科と内分泌内科を二枚看板として更に診療科を発展させたのである。
周知の如く、三輪先生は赤血球酵素異常症の研究で世界に冠する新進気鋭の研究者であり、ご自身も述懐されているように柴田先生の精神を実直に継承され、求道者のような研究生活をまっしぐらに歩まれた。奥様の言葉を借りると、先生は貧血の研究者ならぬ「金欠病」の研究をしているとのことであった。
私は、その後幾つかの研究所や大学を経て多くの指導者に巡り合えた。幾人かの方々を挙げると、ミシガン大学のニール教授でありタシアン教授であるが、お二人とも人柄は異なるものの、研究に対する厳密さをしっかりと求められた。筑波大学の及川先生はすでに述べたが、大変温厚で篤実なお人柄であった。
高知医科大学臨床検査部に10年間お世話になったが、自動検体搬送とロボットに情熱を傾けられた佐々木匡秀教授は一見放胆でありながら、気配りの人でもあった。これらの指導者の方々はそれぞれに個性豊かで、反面教師的な部分も含めながら偉大な存在であったことに今更ながら感慨に浸っている。
私は今、不肖の息子のように迷走を重ねた末、130床の病院内科医として勤務している。ここ15年間、倉敷中央病院臨床検査部長を経てから内科医への復帰は、当初かなりの戸惑いがあった。それは新規薬剤名の煩雑さと画像診断の驚くべき発展である。我々の世代は安易な臨床検査や画像検査のオーダーをきつく戒められたが、現実は目の前の診療を滞りなく捌くために、心ならずも多種類の検査オーダーをしているわが身にはたと気付くことがある。
偉大な先達を霞みの彼方に仰ぎ見ながら、抜き差しならぬ現実という大きなうねりに浮沈している己を醒めた目で眺めている。