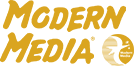バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- ハンセン病の歌人
2012年6月号(第58巻6号)
ハンセン病の歌人
清瀬の多磨全生園に隣接して国立ハンセン病資料館があり、いろいろな展示もおこなっているが、ここの運営検討委員会の座長を頼まれている。委員は博物館の専門家、弁護士、ジャーナリスト、大学教授など有識者に元患者も加わって、年2回開催される。旧約聖書の昔から、ハンセン病患者は差別を受けてきた。ドイツ語の病名Aussatzも、中世に都市を囲む城壁内に患者を入れないことに由来している。日本では癩予防法で患者は全員が療養所に強制隔離された。結節で顔貌が変わり、結節が崩れると化膿、悪臭を発し、病変が目に来ると失明、喉に来ると呼吸困難、そのほか神経麻痺による障害など、悲惨極まりない状態になる。さらに家族から無理に引き離された悲しみの深さも察するに余りある。この苦悩と悲しみのどん底から、感動的な詩歌や文学作品が生まれた。「また更に生きつがむとす盲我 くずれし喉を今日は穿ちて」喉頭に病変がきて気管切開を受けることになった明石海人の歌である。海人は28歳の頃発病、長島愛生園に入所して昭和14年38歳で亡くなった。入園中、歌の道に入り、その歌集「白描」は世に出ると高い評価を受けた。「父母のえらび給ひし名をすてて この島の院に棲むべくは来ぬ」家族に累の及ぶのを恐れて、本名を名乗れなかった心情に胸が痛む。「癒えがてぬ病を守りて今日もかも 黄なる薬をししむらに射つ」大楓子油の週3回注射が唯一の療法であったが、結節の吸収効果があったとしても一時的にすぎず、治療に携わった世界中の医師たちの努力も、この病を治すことは出来なかった。容易に完治させ得るようになったのは、プロミン、リファンピシン、ニューキノロンなど化学療法剤が世に出たからである。これを見ると、治らぬ病に対する臨床医の無力をつくづく感じさせられる。治らぬ病気を治せるようにするのは薬学研究からの貢献が不可欠であり、臨床医の役割は治せる病気はきちんと治し、まだ治せない病には患者を支え、慰めることにあると言えよう。