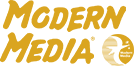バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- ここまで治るリウマチ
2011年12月号(第57巻12号)
ここまで治るリウマチ
私の師匠であった故勝正孝先生は感染症とリウマチを専門分野としていた。私はアメリカ留学時、免疫遺伝学の教室で勉強した。日本に帰り勝先生の下でリウマチの研究、診療に従事した。あるとき勝先生のお供で栄研化学に出かけた。勝先生は栄研化学の培地の開発に携わっていたが、会社は、当時はやりのリウマチ血清診断試薬の開発を決定していた。その関係でリウマチ分野の勝先生に声が掛かり、私が動員された事になり会社との付き合いが始まった。それはもう40年以上も前の話である。関節リウマチの診断試薬の一つに血清反応が使用されていたが、それを日本に導入しようという事になった。そのリウマチ診断試薬はラテックス粒子を血清IgGでコートし、患者血中のリウマチ因子と反応させそれを凝集反応で検出するという原理的には極めて単純な系である。しかしその製品化となると多くの問題が出て来た。先ず使用するラテックス粒子である。成績の安定性に必要となる、均一な円形粒子を入手する事が困難であった。それにやっと目処がつくと今度は感作抗原であるヒトIgGの検討があった。それら多くの問題を会社全体の努力で乗り越え製品が誕生した。その技術のノウハウは栄研化学の資産となりその後幾つかの製品開発に応用され今日に至っている。
リウマチ因子の存在はリウマチの診断基準の一項目となっている。したがってその検出は診断をより確かなものとした。当時のリウマチ治療の主流は“痛み止め”による炎症の抑制であった。その後数年して抗リウマチ薬が開発され治療の大筋が見えてきたが長期予後となると悲観的なものであった。感染性心内膜炎患者の心弁膜に細菌性有肬を記載し、その後それはオスラーの結節と命名された。その事一つでも分かるように、当時その臨床観察力の確かさで高名な内科医の一人であったオスラー教授でさえもその著書のなかでリウマチの難治性について“リウマチ患者が来院すると私は裏口からそっと逃げ出したくなった”と書いているほどである。
ところがここ10年来、リウマチ治療はその様相を全く変えたといってよい。今日では発症1年以内に診断し、適切な治療を施行すれば関節症状の消失という臨床的寛解が70~80%の患者で達成できる。それに満足しないリウマチ専門医はその治療目標のハードルを上げ骨破壊進行抑制という寛解、さらには機能的寛解を目指している。
この事は患者さんにとってはさらに大きな意味がある。リウマチはその治療パラダイムの変化により、これまでリウマチというと“車椅子や寝たきり”の状態を考え暗い響きのあったリウマチに対する将来像を一気に変えてしまった。若い患者の中には治療を受けながら仕事を継続し育児と両立させている多くの患者さんが増え、その方々から寄せられる喜びの声は私達の診療の励みとなっている。