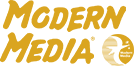バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 核心をつく情報を導き出す知力
2011年6月号(第57巻6号)
核心をつく情報を導き出す知力
本誌2月号の著書紹介欄に拙著「インフルエンザとインフルエンザ菌」が掲載された。自費出版であるにも関わらずご紹介して頂いたご好意に深く感謝する次第である。本書は小生の身近に居られる若い研究者に対して、病原微生物に関わる古典的な医学論文に解説を加えた書をお送りすることが、何かの折に役に立つと考えて書いたものである。
お送りした方々からは「もう少し図表を入れて欲しかった。そうすればもっと読み易かった」とのお言葉を頂戴した。確かにお説のとおりである。しかし、1900年初期の医学論文には抄録に類似する原著もあるが、数十例に亘る動物実験の結果を克明に30頁以上に亘って記述している論文も多く、それらのほとんどに図表は用いられていないのである。当時の研究者はこのような記述のみの論文から如何にして確固たる見解を導き出したのだろうか。恐らく、多様な情報源から核心を突く情報を導き出す知力に勝れていたと思わざるを得ないのである。しかし、このような知力は現在でも必要なように思われる。
多くの臨床検査では結果のみが返される。その結果から何を考え、何を成せばよいのかという洞察力と行動力が不足していることが、院内感染や医療事故に繋がることも見られている。現在では耐性菌の増加に伴い抗菌薬の適正投与が求められているが、そのためには病原微生物の迅速な検出と病因との関係並びに薬剤感受性の結果をいち早く知ることが大切である。しかし、それは検鏡と培養を主体とする現在の微生物検査だけでは到底達し得ない。耐性化がこのまま進むと、30年後には抗菌薬は感染症薬としての主役の座を保てなくなるであろうとの感がする。近い将来、人類は如何なる方法を以って感染症と向き合うことになるのであろうか。今は微生物検査の迅速診断法の確立とそれが抗菌薬の適正投与への有益な情報になり得る臨床での解析法を急速に構築する必要がある。そのためには読者からの反論や経験をも交流できる場があって欲しいと思っている。