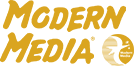バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 花摘む野辺に
2011年5月号(第57巻5号)
花摘む野辺に
花摘む野辺に日は落ちて、此れは故郷をしのぶ歌である。しかし、この歌を教えてくれたのは実は音痴であった私の父親なのであった。親父は音痴であった。子供たちに遺伝されたら困るというので、母はピアノを買って姉に習わせた。姉がピアノを弾かなくなって、そのピアノは弟の私に順が回ってきた。ピアノは疎開した福島に持ってこられていた。その因果で、母と同じ歯医者仲間であった福島に住んでおられたM先生にピアノを習うことになった。月に一度のレッスンがきまったのである。そこで、月に一度はバスに乗って福島に行く事になるのだが、当時の木炭自動車のバスは、行きは下りだから問題なく走るのに、帰りにはバスをお年寄りを除いた全員で降りて、バスを押して坂道を登ったものであった。それにしてものどかな話である。
さて、心臓に好いということで百合の花が開いた場所を覚えておいて、根っこを掘ってきてたべさせていた母が終戦の年の1945年の4月に亡くなってしまった。ピアノは祖父が折角だから続けるようにとの事で相変わらずの福島行きが続いていたが、親父が4月、5月と家にいたことで親父との間に音痴の歌をおそわる羽目になってしまった。思えば親父には宴会などでの持ち歌が2曲だけ在ったようだ。それは「徐州、徐州と軍馬は進む」という軍歌と「花摘む野辺に日は落ちて」の故郷を懐かしむ歌である。第二次大戦も末期であったことで、親父が教えてくれたのは、「花摘む野辺に」の歌であった。「花摘む野辺に日は落ちで、皆で肩を 組みながら 歌を歌った帰り道幼馴染のあの友この友 ああ 誰か故郷を想わざる」音程は別として、この歌詞には亡き母を思い出すことで、胸の中に深く刻み込まれた。そのころの父親にしては珍しく音痴の父親は手を繋いで散歩道を歩いてくれたものであった。しかし、親父はその1週間後に再び戦地の中国へ帰ってしまうのであるが、また会える日も知らずに、一人残していく息子への抱きしめたい気持ちをこらえて、せめて手を握ったものと理解したい。場所は、旧松川小学校から水原へ抜ける旧道を挟んだ田んぼ道であったことは鮮明に記憶している。
「2番;一人の姉が嫁ぐ日に 小川の岸で 寂しさに ないた涙の懐かしさ 幼馴染のあの山 この川 ああ 誰か故郷を想わざる。」そして、この2 番ゆえにあの山、あの川と周りの風景が非常に重要になるのである。
「3番:港に雨の降る夜は、涙に胸も湿りがち 遠く呼ぶのは母(?)の声幼馴染のあの友、この友 ああ 誰か故郷を想わざる。」
この歌詞は音痴の親父に教わったのだが、なぜか東京に出てきて、電車のドアの閉まることに驚いて、寂しさを感じたことがあったことが、思い出される。
松川町のような田舎では列車は走ってから乗り、止まらない前に降りるとしておった習慣から驚いたまでなのであるが、電車のドアが閉まるのに「東京は冷たい所だなあ」と感じて、「都会の寂しさ」に驚いた私が、今に思えば冷たく感じた東京の第一の印象でもあったようだ。しかし、山も川も田舎の松川町のそれとは異なるものであった。その後、私は松川に帰ることはあっても住んだことはない。私には幼馴染のあの友、この友は消滅してしまっていたのである。