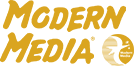バックナンバー
Back Number
2010年1月号(第56巻1号)
著書と編書
最近、大学の図書館や街中の医学専門書店で気がついたのだが、背表紙に「〇〇著」ではなく「△△編」と記された学術書が目立って多くなった。この傾向は、比較的教育色の濃い解剖学などのオーソドックスな学問領域よりも、分子生物学関連の先端科学的領域でとくに著しいようである。
勿論、学問を深く進めようとすればするほど、その間口は狭くなり、研究はより細分化された専門分野に特化することになる。その結果、ある特定の研究分野に身を置く研究者は、いかに優れた頭脳の持主であったとしても、「××学」とでもよばれるようなより広い学問領域を鳥観することがますます苦手にならざるを得ない。それに加えて、限られた狭い専門分野にしか目がゆかず、周辺の学問領域にはほとんど関心をもたない「専門バカ」と揶揄されるような研究者も残念ながら増えている。こうしたことが広い視野を必要とする著書の書き手を少くしていると考えられる。
いささか筆が滑ったが、編書にはない著書の効用とは一体何なのだろうか。これまでモノグラフを何冊か上梓したことのある私のささやかな体験からいえば、自分が誇りと愛着をもつ学問領域についてその科学的重要性と魅力を誰に遠慮することなく自分自身の言葉で綴れることであり、それが1人でも多くの読者に理解され、刺激を与えられるならば冥利に尽きるというものである。そうしたメッセージを確実に読者に伝えるためには、考え方も様々な研究者が分担執筆する編書ではどうしても無理である。同じ理由から著書の場合も1人の著者の単独執筆が望ましいことはいうまでもない。
私が微生物学の駆け出しの徒だった1970年代、最も感銘を受けてくり返し読んだ専門書がある。川喜田愛郎先生の「感染論-その生物学と病理学-」(1964)がそれである。千点を超す文献を引用した730ページもの大著を読み通すには、かなりのエネルギーを要したが、読むたびに新しい刺激を受け、微生物学の全体像や医学・生物学のなかの位置づけも次第に見えるようになった。この名著との巡り合いには今でも感謝している。
1冊の学術書を書き上げるには、奥深くて幅広い知識に加えて、莫大な労力と時間が必要である。その割には学問的にさほど評価されず、下手をすると「何でも屋」と低くみられかねない。しかし優れた著書が与えるインパクトの大きさは、画期的な研究論文にも決してひけをとらない。ある分野で既に一家をなした研究者には、ぜひその知識と能力を生かして後進の道標となる著書を世に出して頂きたいものである。