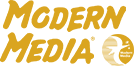バックナンバー
Back Number
2006年4月号(第52巻4号)
形成的刺激
先日、藤原正彦氏の『国家の品格』、養老孟司氏の『超バカの壁』(ともに新潮新書)を続けて読んだ。藤原氏は数学、養老氏は解剖学と、ともに「理系」出身者が分野を超えて社会を論じているのが読者には新鮮なのだろうか、売れ行き好調とのことである。時代の特徴を感ずる。ただ両者には論じ方のスタンスに違いがあるように見受ける。藤原氏の主張は直截で、胸のすくような明解さがあるが、養老氏はいわゆる「バカ」の現象を集めて描写し、読者に考えさせようとしている。これは「紙と鉛筆」でストレートに考える数学者と、多様性のある複雑な生物現象は、理屈で割り切れないことを熟知した生命科学者とのバックボーンの違いではないか。新渡戸稲造に学び、「がん哲学」を機軸とする病理学者である筆者には、二人の考え方はよく理解できる。
戦前、東条内閣の橋田邦彦文部大臣が「科学する心」の大事を説いたとき、それは「政治にゆがめられない」ものでなければならないと「批判する心」の重要性を矢内原忠雄は語った。「批判する心」は学者の良心である。
がん研究には「形成的刺激」という言葉がある。何も起こさない単なる刺激とは違う。がん細胞が発生するのは何もないところからではない。刺激が繰り返した末の、因って起こるところ遠いものである。教育も同じことではないだろうか。私は、若き日に、「寝る前に三十分間、違う分野の本を読め」と言われて、三十年間これを実践してきた。これを通じて、南原繁や新渡戸稲造、内村鑑三や矢内原忠雄の言葉に対する「受け皿」を作ってきたのではないかと、自分の事ながら思っている。それも異分野に触れてこそ、刺激も大きいのでは。先日、ある大学の選択授業で学生たちと新渡戸稲造の『武士道』を時間をかけて読んだのも、それが狙いであった。学生は講義そのものを聴かなくても、脱線の話は喜んで耳を傾ける。「意識してはみ出す」ことを敢えてやることは大切だと実感した。
『いま、わが国に欠けているのは、なかんずく現代を担う青年・学徒の心に訴える、そうした理想と、それから生じるヴィジョンと情熱である』(南原繁)。
樋野興夫『われ二十一世紀の新渡戸とならん』(イーグレープ刊、2003年)
樋野興夫『がん哲学-がん細胞から人間社会の病理を見る』(to be出版、2004年)
樋野興夫『われorigin of fireたらん-がん哲学余話』(to be出版、2005年)