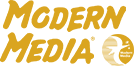バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 「藤沢周平氏と競う」
2006年1月号(第52巻1号)
「藤沢周平氏と競う」
何とも大それたタイトルで恐れ多い気がするのだが、先日世田谷文学館で催された「藤沢周平の世界展」に家内共々足を運んだ時にふと思い出した懐かしい出来事である。
平成3年6月、山形県総務部広報課から1通の郵便が届いた。何事かと封を切ってみると、「いま、山形から・・・」という誌名の縣情報誌への寄稿依頼であった。依頼されたのは毎号連載の「この人」と題するシリーズの次号(No.14, 1991)分で、これには予め指定された郷土の高名な人物を題材にしながら、寄稿者自身の郷土へのかかわりや想いを語ることという注文がつけられていた。私の出生地は山形市近郊の山辺町であり、とり上げる人物はこの町が生んだ第一番の偉人と今も讃えられる明治~昭和初期の外交官・安達峰一郎(最晩年には常設国際司法裁判所長をつとめる)と決められていた。彼の人物像については、父が遺徳顕彰会の会長だったこともあって、子供の頃からよく聞かされていたので、気軽な気持で寄稿を引き受けた。
ところが執筆に取りかかる段になって、参考までにと依頼状と一所に送られてきた前号(No.13, 1991)の「この人」に目を通して驚嘆した。寄稿者は鶴岡市出身の藤沢周平、話題にした人物は女流作家田沢稻舟とある。恥ずかしながら当時私は藤沢周平なる時代小説作家を知らなかった。その私が驚いたのは、彼の名前では勿論なく、描写力の見事さだった。少しも衒うことのない平易な文章で然り気なく綴られた情景や人物が実にリアルに伝わってくるのである。これはとても敵わないと一辺に気が重くなったが、直木賞を授賞した本職の作家なら相手にとって不足はないなどと妙な対抗意識を燃やして原稿用紙に向かった。結果はいわずもがな、筆力の差をいやというほど思い知らされたが、得るものも多かった。それ以来、学術論文であっても言葉の使い方には神経を払う習慣が身についた。それと同時に藤沢文学の大のファンになったことはいうまでもない。