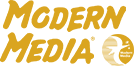バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 喀痰の病原細菌を求めて
2004年5月号(第50巻5号)
喀痰の病原細菌を求めて
故小酒井望先生と筆者が世話人になり、「喀痰研究会」を立ち上げて約10年間、喀痰の中の起炎菌を如何に決定するか、その方法や判断そして、細胞学的炎症診断についても激論してから既に約30~40年の歳月を経た。
その結果、喀痰洗浄法(千葉大学小児科上原一門と大阪市大の三木一門)TTA法(谷本一門)、定量培養法(筆者ら)等が最終的には方法論として残ったが、現在日常的にすべての良質痰について実施されているのは、上原すず子一門の千葉大学小児科系と長崎大学熱研内科とその関連施設のみになった。もちろん底流に流れていた思想は専門家集団であったからグラム染色所見であり、炎症細胞的観察であり、良質痰はさらに必要条件だったのである。
一方この研究会発足前にインフルエンザ菌の培養と同定に成功していたのは、小酒井一門と上原一門、そして筆者らの東北大学第一内科細菌グループだけであった。
さて一挙に今日に至ってこの分野を振り返って見ると強く中央検査部の功罪に思い至るのである。主治医は指示簿に喀痰培養と書くだけであり、良質痰の如何なるかも認識せず、看護師も良く教育されてはいないので、旦々と検体が送られる。その結果は早くても2日後である。直接良質痰のグラム染色所見を見ていた時には15分後には返事がでたのにである。勿論培養は次日で感受性検査はさらに一日延びる。しかし刻々の結果を必要とする重症肺炎では何の役に立つのか、ましてや不良痰が提出されては、さらに誤った結果が報告される。
これらの結果、米国の胸部疾患学会の喀痰無用論に結実した。流石米国の感染症学会は反発した。日本のこれ迄の先人の論文を読み、米国に同調するの愚を知ってほしいのである。良質痰を検査室に正しく提出するまでは医師の責任であり、正に良質喀痰は情報の宝庫なのである。