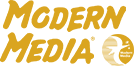バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- エッセイ
- 肺炎原因菌シリーズ 8月号
2015年8月号(第61巻8号)
肺炎原因菌シリーズ 8月号
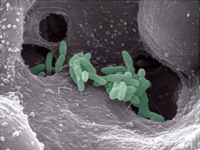
写真提供: 株式会社アイカム
緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa
近年、医療の高度先進化に伴って、そうした治療を受けたことによって本来の生体防御機構に破綻を来した患者(易感染性患者)に好発する病院内感染症(院内感染症)がますます深刻な問題となっている。数ある院内感染症のなかで2番目に多い疾患が院内肺炎である。この場合、原因菌は定着部位である口腔・咽頭から誤嚥によって下気道・肺胞へ到達し、そこで感染が成立して肺炎が起こると考えられる。院内肺炎は、重症化しやすく、院内感染による死亡の最多原因であり、その死亡率は20~50%と高く、とくに人工呼吸器を装着している患者に発症する肺炎(人工呼吸器関連肺炎)の死亡率は50~70%にも達する。大きな脅威となった院内肺炎の原因菌として、黄色ブドウ球菌に次いで多いのが本号でとり上げる緑膿菌にほかならない。
緑膿菌は、グルコース非発酵性の偏性好気性グラム陰性桿菌であり、quorum sensingシステムをもつことやバイオフィルムを形成することでもよく知られる。本来湿った自然環境(土壌、植物、野菜など)中で発育・生存しているが、栄養要求性が低いので栄養分の乏しい院内環境中にも広く生息する。様々な病原因子をもつものの、健常者に感染症をひき起こすことはなく、院内肺炎をはじめ敗血症/菌血症、慢性気道感染症、感染性心内膜炎といった難治性の重篤な感染症がみられるのは、癌化学療法、人工呼吸管理、広域抗菌薬投与、大手術の術後、広範囲熱傷などのリスク因子をもつ入院患者にほぼ限られる。それだけに、これらの感染症の治療には強力な抗緑膿菌活性をもつ抗菌薬(抗緑膿菌薬とよばれる)の使用が不可欠である。
緑膿菌はもともと多くの抗菌薬に抵抗性であり、抗緑膿菌薬としてこれまで治療に用いられてきたのは、ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系、アミノグリコシド系およびキノロン系の一部の抗菌薬に限られていた。さらに厄介なのは、近年、そのなかの複数の抗菌薬に幅広く耐性を示す多剤耐性緑膿菌(multi-drugresistant Pseudomonas aeruginosa; MDRP)が出現したことであり、これが緑膿菌感染症の治療をますます困難にしている。
こうした状況にあることから、より優れた緑膿菌感染治療法の開発はきわめて重要な研究課題であり、そのために緑膿菌肺炎の動物モデルがしばしば利用される。本号の表紙に示すのは、カルバペネム系薬剤の有効性を検討するための動物試験を行った際に撮影した感染肺組織の走査型電子顕微鏡写真である。免疫抑制剤による前処置を行ったラットの片肺に寒天ビーズ法を用いて緑膿菌(IID 1088株)を感染させ、その約10時間後に採取した肺組織の標本を作製し、写真を撮影した。気管支内への菌接種からさほど時間が経っていないが、すでに肺胞腔内に到達した緑膿菌は増殖を始めており、小さな集簇を作っている(緑膿菌を緑色に着色)。免疫抑制処置を行ったためか白血球浸潤はほとんど認められない。感染18時間後には肺胞腔は緑膿菌で充満された。

写真と解説 山口 英世
1934年3月3日生れ
<所属>
帝京大学名誉教授
帝京大学医真菌研究センター客員教授
<専門>
医真菌学全般とくに新しい抗真菌薬および真菌症診断法の研究・開発
<経歴>
1958年 東京大学医学部医学科卒業
1966年 東京大学医学部講師(細菌学教室)
1966年~68年 米国ペンシルベニア大学医学部生化学教室へ出張
1967年 東京大学医学部助教授(細菌学教室)
1982年 帝京大学医学部教授(植物学微生物学教室)/医真菌研究センター長
1987年 東京大学教授(応用微生物研究所生物活性研究部)
1989年 帝京大学医学部教授(細菌学講座)/医真菌研究センター長
1997年 帝京大学医真菌研究センター専任教授・所長
2004年 現職
<栄研化学からの刊行書>
・猪狩 淳、浦野 隆、山口英世編「栄研学術叢書第14集感染症診断のための臨床検査ガイドブック](1992年)
・山口英世、内田勝久著「栄研学術叢書第15集真菌症診断のための検査ガイド」(1994年)
・ダビース H.ラローン著、山口英世日本語版監修「原書第5版 医真菌-同定の手引き-」(2013年)