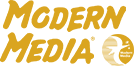バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- エッセイ
- 新・真菌シリーズ 10月号
2014年10月号(第60巻10号)
新・真菌シリーズ 10月号

写真提供 : 株式会社アイカム
アスペルギルス・フラブス Aspergillus flavus
A.flavusは、アスペルギルス症のすべての主な病型(侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、アレルギー性肺アスペルギルス症など)を通して、A.fumigatusに次いで2番目に多い原因菌である。臨床微生物検査室では汚染菌としてもしばしば分離される。本菌が環境中に広く生息しているためと考えられるが、とくに食品分離例の報告が最も多いことから食品との深い関係がうかがわれる。
A.flavusをめぐっては、医真菌学というより食品衛生に深くかかわる2つの問題がとくに注目されてきた。1つはカビ毒(マイコトキシン)産生菌として働くことであり、もう1つは食品産業に欠かせないアスペルギルス・オリザエ(「こうじかび」)A.oryzaeと同一菌か否かという問題である。
1960年、その年の春から夏にかけてわずか数カ月の間に七面鳥の雛鳥が100万羽近くも死ぬという大事件が英国で起こった。原因不明のため初めはターキーX(エックス)病とよばれたこの病気は、やがて飼料に使われたピーナッツ油を汚染したA.flavusによって産生されたマイコトキシンによる中毒症であることが判明したのである。分離同定されたこの毒素は、産生菌であるA.flavusにちなんでaflatoxin(アフラトキシン)と命名された。アフラトキシンの動物に対する毒力は、数あるマイコトキシンのなかでも最強の部類に入るし、ヒトでも肺癌をひき起こすなど発癌性も有することから、わが国の食品衛生管理上最も厳重な監視の対象となっている。
2番目の問題は、A.flavusと日本の食品製造に欠かせないA.oryzaeとが形態学的にほとんど区別がつかないほどよく似ていることから生じた。両菌は分類学的にきわめて近縁であるばかりか、同一菌だと主張する外国人研究者も少なくない(流石にそういう研究者は日本人の中には私の知る限り1人もいない)。そのせいで一時台湾などは日本の味噌やしょうゆの輸入を禁止したほどである。この件に関しては、国内で使用されている「こうじかび」について大規模な調査が行われ、幸いにもアフラトキシン産生株が1株もなかったことが確認されたことで一応の結着をみたのであった。しかし分子生物学的解析が可能な時代に入ると、A.flavusとA.oryzaeの異同が新たな論議の的となり、両菌の全ゲノム構造の比較やアフラトキシン合成にかかわる遺伝子の存在・発現についての研究が盛んに行われている。現在のところ、両菌は分子系統のうえでもきわめて近縁な菌種か、さもなければ同一菌種でありながら生息環境の違いから種々の発現能力に差を生じた異なるエコタイプ(ecotype)ではないかと考えられている。いずれにせよ私達日本人にとっては大いに気になる問題であり、今後の研究の展開に注目したい。
コロニーもそうであるが、A.flavusの顕微鏡像はA.fumigatusとは著しく異なる特徴をもつ。分生子柄はより長く(400~800 μm)、成熟するとその先端部すなわち頂嚢直下の部分の表面が粗く、棘状になる。またフィアライド(単列性のものと複列性のものが混ざっている)が頂嚢のほぼ全体を覆い、しかも放射状にゆるく広がる。フィアライドの先端には黄緑色~オリーブ色の分生子が生じるが、そのレンサが短くて不規則に並ぶために、フィアライドと一体になってみえる。その結果、この写真のように分生子頭全体は花びらが開いた黄色い草花にも似た可憐な姿を呈している。

写真と解説 山口 英世
1934年3月3日生れ
<所属>
帝京大学名誉教授
帝京大学医真菌研究センター客員教授
<専門>
医真菌学全般とくに新しい抗真菌薬および真菌症診断法の研究・開発
<経歴>
1958年 東京大学医学部医学科卒業
1966年 東京大学医学部講師(細菌学教室)
1966年~68年 米国ペンシルベニア大学医学部生化学教室へ出張
1967年 東京大学医学部助教授(細菌学教室)
1982年 帝京大学医学部教授(植物学微生物学教室)/医真菌研究センター長
1987年 東京大学教授(応用微生物研究所生物活性研究部)
1989年 帝京大学医学部教授(細菌学講座)/医真菌研究センター長
1997年 帝京大学医真菌研究センター専任教授・所長
2004年 現職
<栄研化学からの刊行書>
・猪狩 淳、浦野 隆、山口英世編「栄研学術叢書第14集感染症診断のための臨床検査ガイドブック](1992年)
・山口英世、内田勝久著「栄研学術叢書第15集真菌症診断のための検査ガイド」(1994年)
・ダビース H.ラローン著、山口英世日本語版監修「原書第5版 医真菌-同定の手引き-」(2013年)