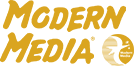バックナンバー
Back Number
2015年9月号(第61巻9号)
〇ビルとビルとに挟まれたほんのささやかな小道にさえ、どこからかキンモクセイの香りを乗せた爽涼な風が吹き抜け、あたりもだいぶ秋らしくなってきた。
空を見上げれば、縮れたような、ざらついた白い雲の群れ、その向こうには紛れもない青空が続いている。下界の雑踏をものともしない空の静けさに吸い込まれそうになる。しばらく眺めていたら、天と地が逆さになったような錯覚に陥り、誰一人立ち入ることのない、どこまでも続く真っ白な砂浜と穏やかな海を見たように思った。
〇秋といえば、中原中也の詩に「秋」という作品がある。
次はその最初の一節である。
昨日まで燃えていた野が
今日茫然として、曇った空の下(もと)につづく。
一雨毎に秋になるのだ、と人は云ふ
秋蝉は、もはやかしこに鳴いてゐる、
草の中の、ひともとの木の中に。
(現代詩文庫1003中原中也詩集/思潮社)
この詩にも出てくる「秋蝉」とは、立秋を過ぎてからも鳴く蝉全般のことをいう。9月上旬頃まで鳴く蝉には「ミンミンゼミ」「アブラゼミ」「ツクツクボウシ」などがあり、9月中旬頃までは「ヒグラシ」、10月頃までは「チッチゼミ」といって、チッチッ…と鳴き続ける体調2-3センチほどの小さな蝉の種類があるらしい。場所や時間帯によっても鳴く蝉が異なるので、これらが同じ場所で一斉に鳴くようなことはないそうである。
激しい夏の季節から静かな秋へと移ろう頃はどこか寂しい。勢いの衰えたとある草叢に立つ木の中で、やがて消えゆく運命に気がついたように懸命に鳴く蝉の声はさぞやさびしく響くだろうと感慨にひたっていると、「春蛙秋蝉(しゅんあしゅうぜん)」などという四字熟語もあって、春に鳴く蛙や秋に鳴く蝉はやかましいだけで何も役に立たないことから、ただうるさいだけの無用な言論の意味だという。聞く者の心ひとつで、ものの捉え方はこうも違うものかと思い知らされる一例である。