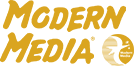バックナンバー
Back Number
2021年2月号(第67巻2号)
〇暖かく明るい春の訪れを心待ちにする思いから、1 年のうちで一番短いはずが、時の進みが遅く、長くも感じられる2 月。春めいてきた日差しに安堵していると、恐ろしく冷え込む日も多い。まだまだ油断はできないものの、どっかりと居座っていた冬将軍も、そろそろよその国に向かおうと旅支度を始める頃。同じ寒さも、3 月になれば〝もう春なのに″と流行遅れ扱いをして、さほど気にならなくなるから「気の持ちよう」とはよく言ったものだ。
〇冬の間首のまわりに巻き付いて寒さから守ってくれたマフラーも、もうじき長いお休みに入る。そういえば、気づかぬうちにあまり聞かなくなった言葉に「襟巻」がある。襟巻には、マフラーのように防寒のためのもの、カウボーイのネッカチーフのように砂や塵などを避けるためのもの、また、装飾としてのスカーフやストールなど、さまざまなものがあり、そのものずばり「首巻」の異名もある。
人と襟巻の歴史は古く、国によって様々な形状のものがある。古代ギリシャでは、大判の1 枚布で上着として着用されていた「ヒマティオン」という衣服も、インドの「サリー」も広くは襟巻に含まれる。
日本では奈良時代に、女性が首からに肩に巡らせた細長いた領巾(ひれ)(比礼・比例)という衣装があり、こちらは装飾や防寒というより、毒蛇や害虫から身を守る呪術的な意味あいで身に付けられていた。天女が絵に描かれるとき、衣の上に纏い、風になびかせているひらひらした細長い布のことでもあり、こちらはとくに「天津領巾(あまつひれ、津は「の」の意味)」と呼ばれる。万葉集には「秋風の 吹きただよはす 白雲は 織女のたなばたつめ)の天津領巾かも」と、想像力豊かでロマンチックな歌人が詠んだと思われる句も残されている。江戸時代の日本では、防寒としての襟巻は病人や年寄りが使うものであったが、明治になると編み物が流行し、誰もが毛糸の襟巻を使うようになった。
東洋で誕生したショールは18 世紀にヨーロッパで流行し、日本では和装の際に専ら用いられた。また今では、ボアというと毛足の長い素材でできた織物を指し、コートの襟や袖口などに装着されるが、古くは毛皮や羽根など柔らかい素材でできた細長い襟巻の名前であり、その見た目から、4 メートルもある大蛇の名に由来しているそうである。
〇衣服に関する言葉一つとっても、「襟巻」や「とっくり(徳利):タートルネック」、「えもん(衣紋)かけ:ハンガー」、「つっかけ(突き掛ける):サンダル」、「チョッキ(直着、ちょっと着る):ベスト」など、古臭くてちょっとカッコ悪いけれど、長く愛されてきた呼び名がいつの間にか忘れ去られていくこと、先人達が頭をひねり、ユーモアも交えて絶妙に表現した日本の名前が、あっけなく海外の言葉に置き換えられていくことを残念に感じてしまう今日この頃である。