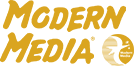バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 臨床検査の価値を高めたい
2011年8月号(第57巻8号)
臨床検査の価値を高めたい
全人医療という言葉は昔からあるが、この頃また聞くようになった。また良い医師を養成するために新しいMedical Schoolをつくる必要があるという人もいる。終末期医療の具体策がないという声もある。今の医学に世間の人は何か不足を感じている。それに臨床検査はもっと役立つと思う。
現在の医学は病気を具体的な形で捉え、これを除去する事を目標に発達し成果を収めてきた。それは獲物を狙って狩をする姿に似る。我々農耕民族とは違い、身体の局所に注目が注がれ、人全体を余り見ない傾向がある。
私は新米医師の頃、数拾年前生化学が急速に進歩するのをみて、血液の臨床化学的検査によって病気がわかるのかと思い(実際は違っていたが)、柴田進先生に付いて倉敷から山口医大に赴いた。そこで光電比色法による臨床検査法の改良開発が精力的に行われた。やがて簡易化、微量化、機械化、システムと進み、日常検査としてすっかり普及した。現在は検査法の標準化が進められており、やがて検査データの共有化が実現するであろう。これはこの仕事を始めた頃からの念願であったが、漸く近付いてきた。
さて次の問題はどんなデータベースを作るかである。ただ蓄積しただけでは使い物にならない。検査からの健康管理、身体異常の早期発見、病気の予後判定などに役立てようとするなら、その目的に応じた編集をする必要があり、データ処理の研究も要るだろう。堅牢で精度の高い再現性のある検査データは、医療の中では他に少ない貴重な資料である。EBMではないが、この分析から実際の治療に即した新しい病名が生まれたり、従来の病名の定義の修正や変更を迫られるかも知れない。今使われている病名の多くは臨床検査以前につくられたものであり、これに検査結果をつき合せようとしているから無理や不足な所があって当然である。
現在の医学は原因療法を第一としてきたが、その限界があったり原因不明なときは対症療法が大事である。数量化した検査結果は病状の軽重の判定に役立つ。但し人間の体力、復元力には個人差があるから、数字だけからパニックだとか軽重を云々するのは危険である。検査結果の判断は患者情報が必要であり、この部分はアートである。検査そのものはサイエンスであって、機器・試薬はメーカーに依存する。このあたりが臨床検査の活用の難しい所である。
紙数が尽きたが、昔漢方の名医細野史郎先生から聞いた言葉がある。全く健康の状態は存在しないと。これからの課題は検査結果と患者状態との結びつきであると考える。