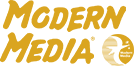バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- エッセイ
- 虫林花山の蝶たち(10):
2010年10月号(第56巻10号)
虫林花山の蝶たち(10):
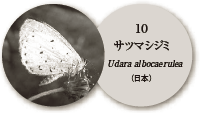
南方熊楠とサツマシジミ Albocaerulean
サツマシジミは薩摩の国(現在の鹿児島県)で最初に見つかったので、サツマという名前がついたシジミチョウです。実際、この蝶は日本では九州から中国、四国地方や紀伊半島までと南方系の分布を示します。しかし、近年は温暖化の影響か大阪や京都でも発見されているようです。本種のオスの翅表は明るいブルーに前後翅とも白い大きな紋がありとても綺麗で艶やかです。メスは黒地で、やはり同様の白い紋があります。裏面が雪のように白いのも本種に特徴的です。
私がこの蝶に初めて出会ったのは紀伊半島(和歌山県)でした。数年前の10月に日頃親しくしている和歌山医科大学のK教授が和歌山市内で学会を開催することになりました。もちろん、私もその学会に参加しましたが、学会終了後の週末は、日本を代表する博物(生物)学者として知られる故・南方熊楠(みなかたくまぐす)が生まれ育った紀伊半島の海岸をぶらりと歩いてみたいと思いました。もちろん紀州の蝶の撮影も兼ねているのはいうまでもありません。
南方熊楠は幼少時を和歌山県田辺町(現田辺市)で過ごし、東京で学生生活をおくった後、アメリカに渡って動植物の研究に没頭しました。その後、イギリスの大英博物館に入りましたが、暴力事件を起こし、和歌山県の田辺市に戻り再び研究を続けたそうです。彼は粘菌の新しい属の発見をはじめ、多くの論文を著していますが、生涯を在野で過ごしたというのもユニークです。
学会終了後、すぐに和歌山市から特急「黒潮」に乗って半島の先端に向かいました。小さな海辺の町に宿をとり、翌日、海岸線につけられた狭い小道に沿ってゆっくりと歩いてみました。本州南端のこの地では、タブやシイなどの照葉樹の林が、波が打ち寄せる海岸近くまでせり出し、岸壁の間の開けた海岸には小さな漁港がつくられていました。そんな長閑な景色をぼんやり見ていると、英国で暴力事件を起こし、傷心で帰国した南方熊楠がこの地に戻ってきた気持ちが理解できるようでした。
歩き出して間もなく、道路脇のセンダングサの花にひときわ白いシジミチョウが吸蜜しているのを発見しました。それはルリシジミよりも大きくて翅裏からも翅表の白い大きな紋が透けて見えました。サツマシジミに違いありません。サツマシジミでそれまで未撮影の蝶でしたので、喜んで撮影しました。その後、海岸に近い草原や林の縁のセンダングサの花で本種が吸蜜している姿を何度も見つけることができ、またサンゴジュなどの広葉樹の葉上で翅を開いて日光浴する姿も見ることができました。もっと散歩したい気持ちを抑え、お昼過ぎの三重県の熊野行の電車に飛び乗りましたが、名古屋経由で我が家に到着したのはすでに深夜になっていました。
以来、サツマシジミを見ると、南方熊楠とともに美しく長閑な紀州の海岸線が思い出されます。
虫林花山の散歩道:http://homepage2.nifty.com/tyu-rinkazan/
Nature Diary:http://tyurin.exblog.jp/

写真とエッセイ 加藤 良平
昭和27年9月25日生まれ
<所属>
山梨大学大学院医学工学総合研究部
山梨大学医学部人体病理学講座・教授
<専門>
内分泌疾患とくに甲状腺疾患の病理、病理診断学、分子病理学
<職歴>
昭和53年…岩手医科大学医学部卒業
昭和63-64年…英国ウェールズ大学病理学教室に留学
平成2年… 山梨医科大学助教授(病理学講座第2教室)
平成8年… 英国ケンブリッジ大学病理学教室に留学
平成12年…山梨医科大学医学部教授(病理学講座第2教室)
平成15年…山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
<昆虫写真>
幼い頃から昆虫採集に熱を上げていた。中学から大学まではとくにカミキリムシに興味を持ち、その形態の多様性と美しい色彩に魅せられていた。その後、デジタルカメラの普及とともに、昆虫写真に傾倒し現在に至っている。撮影対象はチョウを中心に昆虫全般にわたり、地元のみならず、学会で訪れる国内、国外の土地々々で撮影を楽しんでいる。