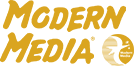バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- エッセイ
- 虫林花山の蝶たち(6):
2010年6月号(第56巻6号)
虫林花山の蝶たち(6):
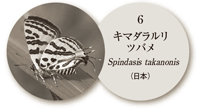
夕方の踊り子 キマダラルリツバメ Japanese Silverlines
キマダラルリツバメは翅の裏面がトラ模様で、オスの翅表にはコバルトブルーの大きな紋が広がるとても美しいシジミチョウです。日本では中国地方から東北地方にかけて飛び石状に棲息地が知られています。また、本種はサクラ、キリ、クワなどの古木につく特別なアリに育てられるという特殊な生態を持ちますが、近年の開発などによる環境の悪化で、棲息地のいくつか消滅してしまいました。現在では環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種に登録されています。
本種はその希少性と美しさから、日本の蝶マニアの間でとても人気があって、キマダラルリツバメの名前を短縮して「キマルリ」と親しみをこめて呼ばれています。
キマルリは山梨県にも棲息しているので、何度かその棲息地を訪れたのですが、結局これまで一度もその姿を見ることが出来ずにおりました。長年、「目の上のタンコブ」ならぬ「目の上のキマルリ」になっていたわけです。
本種に初めて出会えたのは、ある年の6月下旬、福島県の小さな村でした。そこはキリの古木が林立していて、いかにも本種が棲息していそうな場所でした。しかし、暑い日中にさんざん歩き回って探したにも関わらず、憧れのキマルリは見つけることができませんでした。午後3時半を過ぎて、少し日が傾き始めた時に、目の前を素早く横切る小さなシジミチョウが突然現れました。とにかく、非常に早く飛ぶのと小さなその姿が周囲の環境に溶け込んでしまい、それがキマルリなのかどうかも確認出来ないままにとうとう見失ってしまいました。がっかりして、しばらくその場に立ちつくした後、足を踏み出したその先の灌木の葉に、なんと翅を開いて静止している美しいオスのキマルリがいたのです。その時の翅表の深いコバルトブルーの輝きは今でも忘れることができません。周りを見渡すと、何頭ものキマルリが飛び交っていて、まるで小さな踊り子たちが夕方の光の中で踊っているようでした。
先日、中国の福建医科大学との大学間交流事業のために、福建省の福州市を訪れる機会がありました。日中に少し時間が出来たので、市内の緑が残る公園を散歩してみました。しばらく歩いてランタナの花を何気なく見ると、そこには日本のものとほぼ同様のトラ模様を持つ小さなシジミチョウが吸蜜していました。日本のキマルリとは別種のようですが、よく似ているので、興奮しながら撮影しました。
そういえば、今年は寅(トラ)年ですので、トラ模様の翅を有するキマルリは寅年の蝶ともいえますね。
虫林花山の散歩道:http://homepage2.nifty.com/tyu-rinkazan/
Nature Diary:http://tyurin.exblog.jp/

写真とエッセイ 加藤 良平
昭和27年9月25日生まれ
<所属>
山梨大学大学院医学工学総合研究部
山梨大学医学部人体病理学講座・教授
<専門>
内分泌疾患とくに甲状腺疾患の病理、病理診断学、分子病理学
<職歴>
昭和53年…岩手医科大学医学部卒業
昭和63-64年…英国ウェールズ大学病理学教室に留学
平成2年… 山梨医科大学助教授(病理学講座第2教室)
平成8年… 英国ケンブリッジ大学病理学教室に留学
平成12年…山梨医科大学医学部教授(病理学講座第2教室)
平成15年…山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
<昆虫写真>
幼い頃から昆虫採集に熱を上げていた。中学から大学まではとくにカミキリムシに興味を持ち、その形態の多様性と美しい色彩に魅せられていた。その後、デジタルカメラの普及とともに、昆虫写真に傾倒し現在に至っている。撮影対象はチョウを中心に昆虫全般にわたり、地元のみならず、学会で訪れる国内、国外の土地々々で撮影を楽しんでいる。