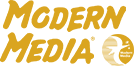バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 細胞診の底力(パートII)
2025年9月号(第71巻9号)
細胞診の底力(パートII)
病理検査/病理診断では、細胞診は補助診断、組織診は最終診断(確定診断)として扱われるのが一般的である。しかし、細胞診は病態の本質の理解にかかわる面では重要な役割を果たすこともあるという事例を子宮頸癌についてとりあげ、「細胞診の底力」と題して本誌の随筆欄に寄稿したことがある(第61 巻5 号)。細胞診をいわば陰の立役者としてスポットライトをあててみた。
だが、細胞診の“底力”は、黒子にとどまるものではない。組織診を行わなくとも細胞診の判定結果のみで十分な臨床的指針がえられる領域がある。本稿では甲状腺細胞診を取りあげてみたい。
昭和の比較的末期になって、甲状腺病変判定に穿刺吸引細胞診が導入された。その前までは、治療開始前の最終診断は針生検組織診の独壇場だった。しかし穿刺吸引細胞診が登場すると、判定内容は針生検組織診と互角かそれを上回ると評価された。穿刺吸引細胞診は針が細いので、無麻酔で施行できる。一方、太い針で行う針生検組織愼では、副反応の発生率が高い。この様な事情の中、穿刺吸引細胞診が専ら用いられる様になり、今日に至っている。
話は変わるが、2011年3月に東日本大震災による福島第1 原発事故が生じたが、小児甲状腺癌発生のチェックのために「福島県民健康調査」がスタートした。事故当時18 歳以下の約38 万人の福島県民は、生涯にわたり定期的に超音波検査を受けることになった。超音波異常所見の内容により、穿刺吸引細胞診が行われる。このプロジェクトでは、穿刺吸引細胞診判定結果は最終診断として扱われ、その後の臨床的対応決定の要として用いられている。ここには針生検組織診が入り込む余地はない。
筆者はこのプロジェクト発足以来、病理コンセンサス会議委員長として細胞診の悪性およびいわゆる疑陽性の判定、手術された甲状腺癌の組織診断を担当してきた。国と福島県がすすめているこのプロジェクトにおける穿刺吸引細胞診の扱われ方は、甲状腺領域の細胞診の診断学上の意義が、的にも確固として位置づけられている1つの例である。