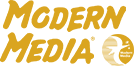バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 高齢者医療と検査値-HbA1cの新提案値について
2025年8月号(第71巻8号)
高齢者医療と検査値-HbA1cの新提案値について
福島医大を定年退職後、地元の病院で、地域医療の一端に加わってきて12年目を迎えます。地域医療とは高齢者医療といっても過言ではなく、私が担当する入院者の多くは後期高齢者で、認知症のみられる方が多い状況です。ヒトは生をうけ、死を迎えることは必然であり、いかに迎えるかの関心も高まっていますが、高齢者医療のさまざまな問題に直面している毎日です。
高齢者の問題の一つに摂食があります。“年を取れば食べれなくなり、自然に死を迎える”のが動物生命の自然経過ですが、ヒトでは、さまざまな栄養補充の手段で命が維持され、寿命延長がなされてきております。糖尿病と診断される高齢者も多いのですが、摂食能が後期高齢者では最も重要な生命予後の規定因子だろうと考え、口に合う食べ物は摂るように勧めて診療しております。
かつて、検査医学を担当し、青壮年の検体を用いて基準値作成を行いましたが、高齢者については困難なものと諦めており、手もつけられませんでした。しかし、高齢者を前にしますと、適正な治療(検査値)指標が無く、それらの設定を切望してきた次第です。このような状況の中、HbA1c値の新たな提案がなされました。2013年の熊本宣言による「7%以下」の目標に対して、「認知の状態」を考慮した改定案が日本糖尿病学会と老年学会の合同委員会から「高齢者糖尿病診療ガイドライン2017」として出されました。細かな分類がされていますが、端的にいえば、軽度の認知症者では上限を8%以下、中等度以上の認知症者では8.5%以下を目標とすべき、さらに、下限値が設定された、というものです。本邦人での検討がどのようになされたのかも知りませんが、認知という難しい要因を加えての現実的な提案で、現場の高齢医療担当者の一人としては歓迎しております。ただ、基準値の問題を、考えてきた者としては、この急に思える提案は、経験的な立場からの値とも愚推いたします。検査医学関係者の関与があったかどうかも知りませんが、医学としての科学的根拠となるような情報を知りたいと思います。
近年のアメリカでのコレステロール値や血圧値の変更も今後の日本の診療に影響を及ぼすものと想定いたしますが、検査医学の専門家は臨床系学会と共同で、高齢者の基準値や病態識別値などの議論を高め、高齢者治療の適正な指標作成という難問にも取り組んでいただきたいと願う次第です。