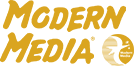バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 世界の医学部を調査
2025年4月号(第71巻4号)
世界の医学部を調査
日本は医学・医療ともに世界一だ。あえて他国の医学教育など参考にすることなぞ無用である。が、世界大学ランキング、論文発表数、文献引用数のいずれをとっても、いつまでもアジアNo.1などと言っていられまい。「医の中の蛙(造語)」であってはいけない。
そんな反省を受け、世界の医学教育を視察し、わが国の医学教育の改善に供することとした。プロジェクトは2007年頃に始まり、10年間で訪問したのは20か国50医学部以上にのぼる。それぞれの国、医学部には個性があり、特有な教育で医師を育成している。政治、経済、文化、国民性などの背景が異なる他国の制度をそっくり導入する必要はない。それでも、海外で行われている教育システムで、参考になる点は導入するべきだろう。良いとこ取りで結構。こんな考えで調査を行い、報告書、論文、学会などで発表してきた。
調査でもっとも思い出に残るのがサモアだ。WHOの要請を受け、韓国、台湾の委員とともにサモア医科大学を視察した。1学年10名前後の学生で、日本の昔の小学校のような校舎で学び、附属病院は扇風機が回る野戦病院(もっとも実物を見たことはないが)のような感じだった。小さいだけに専任教員も5名足らず。教材は主にアメリカから配信されるe-learningだ。
小さな国の医学教育など参考にすることなどないと思われるかもしれない。が、学生は「24 の瞳」よろしく、賢明にe-learning にかじりつくように学修していた。日本のように自宅にPC があるわけでなく、学生は早朝から登校して学んでいた。限られた資源だからこそ学修意欲が上がるのは、教育資源豊かな我が国の学生にも聞かせたい。
サモアでは、日曜日には働いては行けないとの鉄の掟がある。国際視察団といえど、例外ではない。ヤムを得ず(?)、日曜日にはサモアの海に出かけ、珊瑚礁に囲まれ、どこまでも澄み切った海での海水浴。夜はホテルでファイアーショー。思わぬ休日を日韓台の3委員は満喫した。