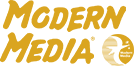バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- 生活の中の博物館
2024年12月号(第70巻12号)
生活の中の博物館
生活している地域を探索すると、身近なところで、誇るべき貴重な史跡が残されていることが判る。近くの大山の麓や七沢(神奈川県)は、古墳が多い地域として知られている。昔から人の住み易い環境が整っていたと想像できる。七沢は七つの沢と書き文字通り、山から流れる川が多い。比較的温暖な気候で、山の小動物、木の実や果実が入手し易すく、海へのアクセスも良い。古墳の多くは開発とともに消失した。ビルや道路などの工事の際に発掘調査が行われ、その後に破壊されてしまうことが多い。古墳があったことを示す石碑や立て看板が目印となる。畑の中に取り残された林や小山として佇む古墳もある。ときに古墳は、1500 年以上にわたり永く人々の暮らしの中で、生活の一部となり保存されてきた。「生活の中の博物館」と称することができる。大山近くの日向薬師に向かう市道沿いに鎧塚(よろいづか)古墳群がある。大きな古墳の周囲に、発掘対象とならない小型の円墳が並ぶ。こんもりした土盛りとして畑の中に取り残されている。土盛りは、農家の方が代々手厚く取り扱ってきた。古戦で亡くなった兵士の墓と言い伝えられ、「塚」と呼んでいる。なるほど、どの土盛りの頂にも地蔵や石碑がある。農作業していたおじさんの話しでは、祟りがあるといけないので、正月にはお飾りをするとのこと。少しでも掘り起こそうとすると、市役所の人が飛んで来て注意される。畑の持ち主としては固定資産税を払っているものの農作物が作れなくて損していると嘆いていた。実際は、兵士の墓でなく、地層の年代から古い時代の古墳であり、当時の豪族の墓であることが判明している。農業を営むおじさんは、古墳時代に住んでいた人々の末裔であろうか?地域の民族資料館での説明では、当時の竪穴式住居の数の動向から、長い年月の間に集落の人数は減少しており、他の土地に移動したと考えられている。地元の農家の方々は後の時代に移り住んで来たことになる。どの時代にも、人々の営みがあり、より良い生活を求めて移り住んだ歴史がある。我々もこの地に移り住んで来た。その歴史を踏まえて、現代の地域社会があり、我々の生活がある。長い歴史における人々の暮らしの積み重ねに思いを馳せると、その重みを強く感じる。「生活の中の博物館」を通して、歴史を学ぶことにより、日々の暮らしの有り難さを改めて感じる。