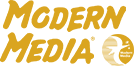バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- 随筆
- ある結核患者の闘病記録
2024年11月号(第70巻11号)
ある結核患者の闘病記録
明治時代の結核患者は手を拱いて死を待つだけであった。明治の元勲大山元帥の令嬢信子をモデルにした徳富蘆花の小説「不如帰」のヒロイン浪子は、肺結核のため離婚されて実家で亡くなり、臨終の言葉「もう女なんぞに生まれはしませんよ」は読者の涙を誘った。
肺結核の死亡率は大正から昭和初期には人口10万あたりの200 前後と高く、衛生行政の大きな課題で、各地に結核療養所がつくられて大気安静療法や人工気胸、あるいは胸郭成形術が行われるようになった。化学療法が主流になったのは戦後のことである。トーマスマンの「魔の山」(1924年)は療養所を舞台にした小説で、マン夫人がダボス療養所に入院し、トーマスもそこに数週間滞在し、その体験をもとにして書かれた。数年前、文芸春秋から出版された「わが心のサナトリウム保生園」は、27歳で発病した著者が、化学療法、胸郭成形術、最後は右肺全摘手術を受けて社会復帰するまでの10年間の闘病記録である。入院患者は会社員や労務者から刺青を入れたやくざもいて、禁煙を守らず、隠れて酒飲む者、花札賭博、喧嘩、夜ナースステイションに忍び込んで夜勤の看護婦を口説く男などがいる一方、ラテン語やギリシャ語を独学していた青年、さらには患者同士、あるいは患者と看護婦が結ばれた例もあり、これらを含めて長年療養を共にした人には療友と言う独特な感慨があると述べておられる。
保生園は結核予防会の新山手病院となり、医科研病院外科教授の藤井先生が定年後に院長として赴任された。藤井先生は数年前に亡くなられ、その追悼式で著者の大場さんにお目にかかって寄贈されたのがこの本である。
私はインターンの時、杉並の久我山病院で当直のアルバイトをしていたが、100 床あまりの結核病棟があり、毎週胸郭成形術が行われていた。当直の晩に患者が喀血すると、ビタミンKや毛細血管増強剤とされたルチンを注射したことを思い出す。当時の院長は結核予防会の北練平先生で、先生は結核の歴史や流行の変遷などを取り上げたルネ・デユボスのThe white plague(白い疫病)を翻訳、出版しておられる。