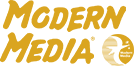バックナンバー
Back Number
- 医学と公衆衛生に関する学術情報誌【モダンメディア】
- バックナンバー
- エッセイ
- 鳥棲む空にて
2025年4月号(第71巻4号)
鳥棲む空にて

ライチョウ
ライチョウの雄です。立山の登山拠点である室堂で撮影しました。時期は4 月の後半でしたが、室堂の標高は2450m です。御覧の通りまだ真冬の様相でした。極寒期には氷点下20 度をも下回るそうで、この高山の厳しい寒さにライチョウは数万年かけて適応してきたのです。
この写真のライチョウは、黒い夏羽が混じり、目の上の真っ赤な肉冠が凛々しく見えます。地味ではありますが、他の鳥にはない精悍さがあるように思います。
高山の厳しい環境に適応し、氷河期から生き延びてきたライチョウも、温暖化による気候変動や登山客が出すゴミなどの環境汚染により、今や絶滅の危機に瀕しています。彼らが置かれている状況は悲観的と言わざるを得ません¹⁾。
保護増殖活動はこれまでにコウノトリやトキで行われました。しかしながら、日本の固有種を残すことはできず、外国産のものを移植しています。日本のライチョウと同種(ライチョウ亜種)は世界中に広く分布していますが、高山という特異な環境で暮らしているのは日本だけです。外国産のライチョウの移植は、コウノトリやトキのケースとは比べ物にならないほど難易度が高い気がします。
この時期の室堂には、厳しい冬山登山に挑む登山客たちが大勢集まります。雷鳥沢から望むと、剣岳の麓に登山客のベースキャンプを眺めることができます。厳しい自然に挑む人々のカラフルなテントは、雪一色の殺風景な景色に彩りを与えています。しかし、真っ白なライチョウこそが、この景色になくてはならない彩りなのだと私は思うのです。
1)1.ライチョウの概要と保護増殖事業計画について(ライチョウ概要資料)(令和 2 年 4 月 7 日)環境省ホームページ
https://chubu.env.go.jp/shinetsu/wildlife/rockptarmigan/index.html
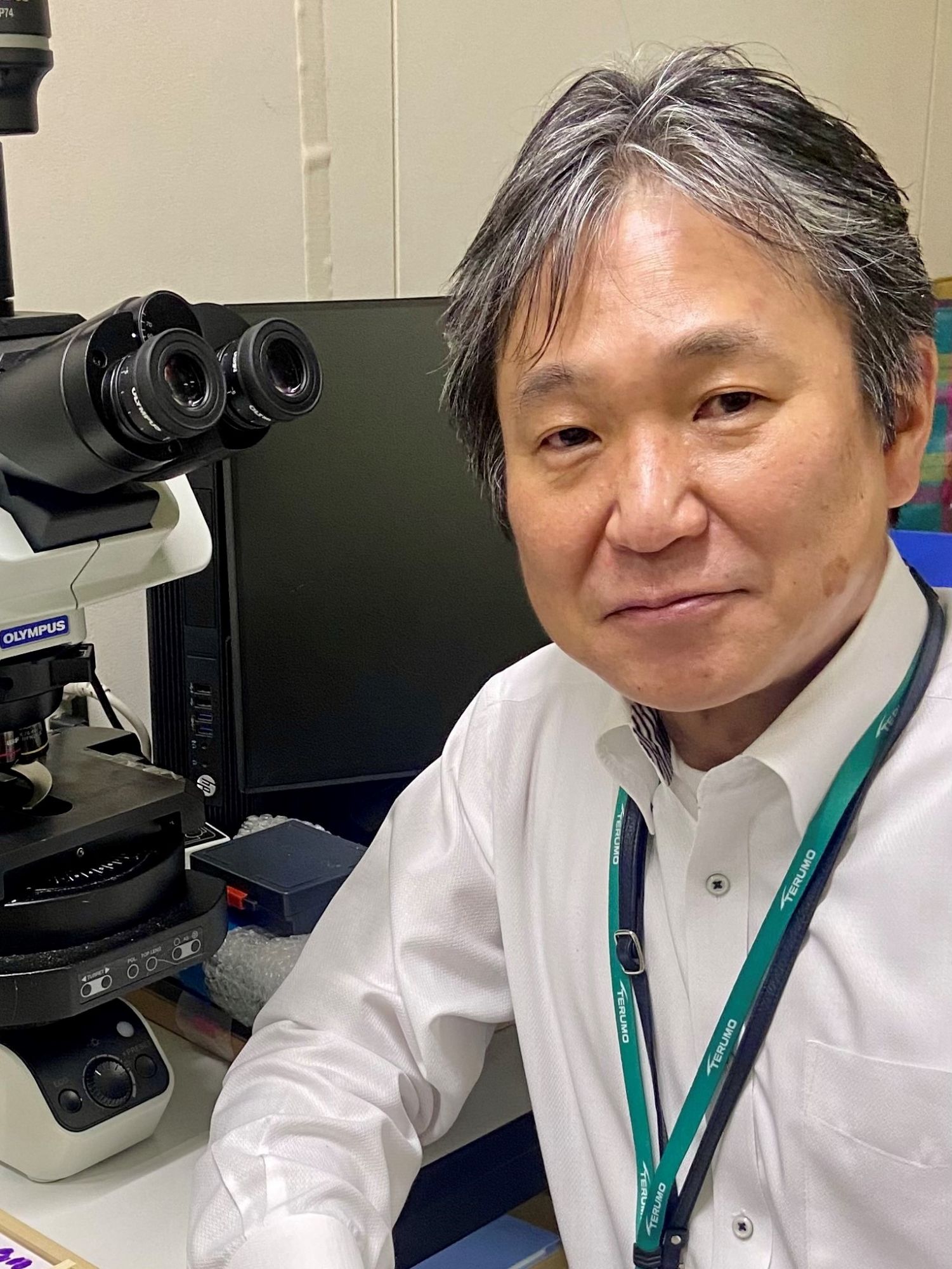
写真とエッセイ 佐藤 秀樹
<所属>
獣医師 日本毒性病理学会認定病理学専門家
テルモ(株)R&Dテクニカルアドバイザー
<プロフィール>
テルモ湘南センター 元主席研究員
テルモバイオリサーチセンター 元センター長
人口血管、ステント、イメージングデバイスなど、種々の医療機器の研究開発に従事。
写真は20代の初めの頃、当時お世話になっていた国立衛生研究所の室長に薦められて。モチーフは主に風景と鳥。
記憶している最初のカメラは、キャノンEOSシリーズの1号機、EOS650。
現在使っているカメラはNIKONで、購入したのはつい最近のこと。
それまで使っていたカメラとレンズ資産を手放して購入し、現在は望遠レンズ購入を検討している。
撮影のモットーとしては、デジタルカメラで撮影の際は、多少ピントが甘くても、その瞬間を逃さずシャッターを切ることが大事だと思っている。